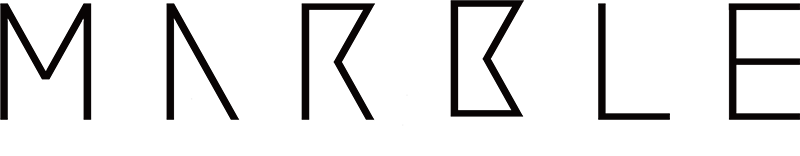「リフォームにあたって、壁はペンキ塗装にしたい」
「せっかくなので、DIYでチャレンジしてみたい」
壁のリフォームをペンキでDIYするのはそれほど難しくないのですが、初めてのときは揃える道具も上手な塗り方も全然わかりませんよね。
この記事では、ペンキでDIYする方法や注意点について初心者の方でもわかりやすいように詳しく解説します。
ペンキとクロス貼りの違い

壁を変える場合、ペンキとクロス(壁紙)を比較検討されることが多いと思います。
どちらもメジャーなDIYですが、作業工程や難易度には違いがあります。
まずは、ペンキとクロス貼りの違いについて詳しく見ていきましょう。
ペンキは、下地の状態によってはそのまま重ね塗りできる
ペンキの場合、下地となるクロス(壁紙)の状態が良ければ、そのまま重ね塗りすることができます。クロス貼りの場合は既存のクロスを剥がすので、ペンキのほうが作業工程は少ないと言えます。
但し、下地のクロスに凸凹がある場合には、その凸凹が反映される場合があります。
そのため、きちんと平面的な仕上がりにしたい場合には、パテ処理をしなければいけません。
また、下地がツルツルの化粧合板やコンクリート、漆喰などの素材の場合もした処理がいります。
その場合には、手間と時間が増えることは覚悟しておきましょう。
ペンキのほうが作業の難易度が低い
ペンキとクロス貼りの違いは、作業難易度の違いです。
クロス貼りの場合には、貼り方に気をつけなければ、シワができてしまうことがあり、仕上がりが難しいこともあります。
一方、ペンキの場合は凸凹なく塗るのはそう難しくありません。
下地処理の状態が悪い場合は、しっかりと既存のクロスをめくり、パテ処理を行う必要がありますが、それはクロス貼りでも同様です。
ペンキでは模様は選べない
ペンキでは一面を塗装することしかできないため、縞模様や花柄などのアクセントは入れることができません。
柄物で仕上げたい場合には、好みのクロスで仕上げる方がよいでしょう。
塗料によっては匂いが気になることもある
ペンキのDIYは、塗料によっては匂いが気になる場合があります。
室内ですので、匂いが苦手な人はツライかもしれません。
ペンキの匂いをさせたくない場合は、水性塗料がおすすめです。
水性塗料であれば、ペンキに含まれるホルムアルデヒドの発散量が少なく匂いも少ないです。
どれが水性塗料かわからない場合には、「F☆☆☆☆(エフフォースター)」という表示があるかどうか確認することもおすすめです。
この表示がされているものはホルムアルデヒドの発散量も少なく、安全な塗料だと言えます。
匂いが気になる場合には、このような塗料を使用しましょう。
壁にペンキを塗るDIYの実際の手順

ペンキに決めたら、いよいよ塗装準備です。
DIYで壁にペンキを塗る場合の手順を詳しく見ていきましょう。
準備するもの
室内の壁を塗装するのに必要なものは以下の通りです。
・新聞紙
・マスカー
・マスキングテープ
・養生ダンボール
・養生テープ
・コーキング
・ローラー
・ハケ
・バケット
・ネット
・塗料
・シーラー(下地の状態に応じて)
では次に実際に塗装する手順について詳しく見ていきましょう。
実際の手順
ではDIYで室内壁の塗装をする実際の手順を紹介します。
養生
まず最初に行うべきなのが、養生です。
塗装ではどうしても塗料が飛散してしまうため、養生が欠かせません。
床はマスカーでは破れてしまう可能性があるため養生ダンボールを使い、壁や天井で塗料が付着して困るものは、マスキングテープやマスカーで養生していきます。
特に建具や床など塗装面に近い部位は、境目を丁寧に抑え養生していかないと、汚れてしまう可能性が高いです。
下地処理
下地の壁の状態に応じて下地処理を行います。
この処理の内容は下地の状態に応じてやることは変わりますよ。
化粧合板でツルツルしている場合には、サンドペーパーで表面を荒く削ってから掃除し、塗料の付着をよくすると塗料が剥がれにくいです。
コンクリート、モルタル、漆喰、珪藻土の下地であれば、シーラーで接着をよくする必要があります。
クロス下地が浮いていたり剥がれたりしている場合には、パテでその下地の面をならす。
状態が悪い場合には全体をパテで補修してください。
下地の状態がよく、手で触って剥がれそうにない状態であれば、軽く雑巾などで拭きましょう。
タバコのヤニやカビなどが残っていると、塗装の仕上がりに反映されてしまう可能性があります。
以上の例を参考に、現状の下地の状態に合わせて最適な処理をしましょう。
ローラーで塗りにくい部分をハケで仕上げる
塗装はきれいに仕上げたいのであれば、2回重ねて塗るのがおすすめです。
まずは塗料をバケットに移しましょう。
塗装する前には、しっかりかき混ぜてから、塗装すると色ムラが出にくいです。
最初にローラーでは届かない部分をハケで仕上げていきましょう。
少しローラーとかぶさるくらいを意識してください。
ローラーで全体を塗装する
次にローラーで全体を塗装していきましょう。
ローラーには、均一に塗料を染み込ませると、色ムラが少なくなります。
2回目できれいに仕上げるため、この段階では少々であればかすれていても問題ありません。
むしろ厚塗りしすぎると、表面にヒビが入る可能性があります。
重ね塗りの前に一度完全に乾燥させてください。
重ね塗りをする
ある程度塗料が乾いたら、重ね塗りを行います。
この時の注意点は1回目と変わりません。
ただし、2回目が仕上がりのため、できるだけムラなくきれいに仕上げることは意識しましょう。
塗装が完了したら、少し乾かしてから、養生をめくります。
この時、完全に乾燥させるではなく、塗装が完了したらすぐでもありません。
完全に乾燥してしまうと、塗料がマスキングにくっついてしまい、壁の塗料が剥がれる恐れがあります。
逆に乾いていないと、剥がす時の衝撃で塗料が飛散してしまいます。
少し乾いたくらいの状態が一番楽にはがせますよ。
もし完全に乾いてしまっている場合には、カッターで境目のところに軽く切れ目を入れておくと、きれいにはがせます。
DIYを行うときの注意点

壁の塗装を行う時の注意点について、ここでは詳しく見ていきましょう。
養生と下地処理は丁寧に
塗装をする時にきれいに仕上げるために一番重要なのが、下地の処理と養生です。
塗膜は薄いもののため、下地の状態がかなり強く仕上がりに反映されます。
剥がれている壁紙は必ず剥がし、下紙が残ることもあるため、パテで処理し平滑にしましょう。
この処理を怠ることで、失敗につながるケースが大部分を占めます。
時間をかけて丁寧に仕上げましょう。
下地処理と同様に、養生も重要です。
塗装の失敗でありがちなものの一つとして、塗料が塗る予定ではないところに付着してしまうことです。
これは養生が甘いことが原因で起こってしまうことが多いため、特に壁や建具の際の部分はしっかりとマスカーを貼り付け塗装中は剥がれないようにしておきましょう。
汚れてもよい服装で行う
塗装工事は汚れても良い服装で行いましょう。
一度付着してしまった塗料は、剥がすのがとても大変で、場合によっては落とせないこともあるため、もう使わないであろう服を着ておくのがおすすめですよ。
できるだけ皮膚や髪の毛は服や帽子で隠しておくと、付着する心配が少なくなります。
まとめ
この記事では、壁のリフォームをペンキでDIYする方法について詳しくお伝えしました。
ペンキでの塗装はDIYの中でも難しくなく、初心者でもきれいに仕上げやすいです。
この機会に室内壁のDIY塗装に挑戦してみてはいかがでしょうか。